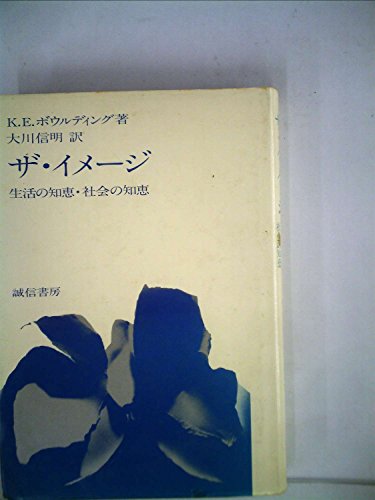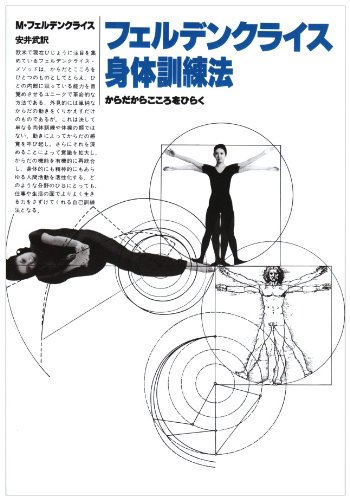舞台公演終えての振り返り
2023年12月29/30と舞台出演した。
お金とってやる舞台は二度目。
初舞台
一度目は全然知らない団体でオーディション受けて出た。演出とかストーリーも好みだったし、最終的にかなり良い感じのものにはなったと思う。 kaishikobo.web.fc2.com
自分はもちろん初舞台なので、そんなに出番も多くはないんだけど、道化役というか、ストーリーに味を与える役だったので、話を壊さないように、求められた役割を発揮できるように、と必死だった。フリーランスだったこともあり、収入かなり減らして稽古した。
役柄にも助けられて、まあまあ面白い立ち回りができた気はする。
今回の舞台
シェークスピアの「お気に召すまま」をがっつり改変したもの。基本的な役の関係性やセリフの一部は残してるが。 社会人向けの公演付きのワークショップの最後の締め。先生(演出/脚本)も演者も知った顔。
役はオーランドで、原作的にはヒロインのロザリンドと並んで主役的ではあるが、まあそこまで主役というわけではない感じ。 あとで書くが、2枚目役というのが大きなハードルだった。
身内の公演なのだが、逆に身内の自己満足な舞台にしたくないって思いがかなりあり、まあまあプレッシャーもあった。 一緒にやるメンバーも結構ガチでやってる人たちなので思いは一緒だったと思う。
やってみての総評
個人的な評価では、1席2000円(映画より高い)の価値はあるんではないかな、とは思った。 普通の舞台は4,5千円は普通で商業だと6000円から1万越え。(個人的に、この値段出してみる価値ある舞台は相当少ないのであまりみに行かないんだが。。。)
全体の舞台としてやりたかったのは以下
- 仲間内ではない人にも楽しんでもらえるものにする
- コメディだが、ドタバタで「笑い」をとるのではなく、ちゃんとドラマがあって笑いも出るような作品にしたい
一応、観客の反応とか雰囲気と先生のフィードバックから、これは達成できたんではないかな、と思う。
自分個人としての振り返り
2枚目役というハードル
舞台では、別に年取ってても若者や子供もできるし、男が女もできるし、そんなに美男美女じゃなくても美男美女役はできる。2枚目の雰囲気を出すのは自分にないのでまあ、チャレンジングだった。ただ、マイケル・チェーホフのメソッドを使って役を作り出せてきてからは、ここはそんなにハードルじゃなくなった。
唐突に恋の詩を読むというハードル
原作にもあるんだが、オーランドは恋の詩を読んで森中に貼り付けるという奇怪な行動をする。それが2枚目役でやるので、唐突感とか、観客に引かれないか、とかそういうのがかなり、最初の方は不安だった。ただ、繰り返すようにちゃんと役ができてきちゃえば、問題にはならなかった。
なんというか、具体的な課題は声出しとか、細かいところはあるけど、意図したものはできたとは思う。
次のステップ
全体として、ある程度やりたいことはできたので、
- 細かい、プロ的な見せ方の部分
なのかな、と思ったけど、多分、不器用なのは変わらない気がするので、もっと長所を伸ばすことをもう一段階求めてもいいと思った。まだ、小手先の技に走るのは早いな、と。
- もっとエネルギーを出して、伝わるような演技ができるようになること
- もっと相手やいろんなものから受け取って、自然に反応できるようになること
- もっと体を柔軟にして、自由に動けるようになること
まあ、継続だな。
あと、明確な弱点である滑舌と発声は訓練したいな
職業ITエンジニア extends ビジネスパーソンではなく。。。
この記事について
qiita.com
自分の考え方は違うので、ここでメモ。
自分はこんな感じがいいと思う。
class ITエンジニア extends クリエーター { } class 職業ITエンジニア extends ITエンジニア implements プロフェッショナル, 組織人 { }
基本的に、商売関係なく、何かを生み出したい、追求したいって衝動のある人がいいな、と思う。
その上で、商売関係なく技術を楽しめることがあるといいって意味で、商売人である前にITエンジニア。
そして、仕事として技術を使う時には、プロとしての振る舞いとか、組織の一員としての振る舞いが必要。
だって、
class 職業ITエンジニア extends ビジネスパーソン { }
だったら、休みの日に趣味でコード書くのができないでしょ。
追記
採用する時とかみてるのは、これも
class クリエーター extends いいやつ { }
英語JVM Advent Calendar ではどんなことが書かれているか
仮想スレッドについて書こうと思ったけど、先に書かれてしまっていたので、ネタ探しで見つけた英語のJVM Advent Calendarにについて紹介。海外のJava界隈の雰囲気が感じられて面白い。コメントは超ざっくり目を通しただけなので、あんま信じないでください。英語苦手でもDeeplとかで読めると思います。
Jet Brainsなんかもスポンサーしている。
1日目 Mockを活用したサービス仮想化アプローチはいかにしてあなたと他人の時間を節約するか
How a service virtualization approach can save your and others' time playing with mocks - JVM Advent
- 複雑な外部サービスの仕様を網羅するんじゃなくて、自分たちでコントロール可能な外部仕様を偽装するサービスを作った方がいいよって話かな。
2日目 2つの都市の物語:ブロッキング呼び出しはどう扱われてきたか
A tale of two cities: how blocking calls are treated? - JVM Advent
- Javaの並行処理の歴史:正直、こちらの記事の方が細かく書かれているかな?
Java in the Box Annex: Virtual Thread導入の背景 - Javaのマルチスレッドの歴史を振り返る
3日目 Eclipse Collectionの隠された宝
HIDDEN TREASURES OF ECLIPSE COLLECTIONS 2022 EDITION - JVM Advent
- Eclipse Collectionの細かい仕様の解説
4日目 そのAPIを消すな!
Don’t remove the API - JVM Advent
5日目 Spring Security の新しい認可サーバー
A new Spring Security authorization server - JVM Advent
- 読んで字の如し。個人的に、あんまり、ちゃんとしたシステムで使う気にはならない機能だけど、内部向けの雑なやつなら使えるのかな。
6日目 JavaのLambdaにおける例外
Exceptions in Java Lambdas - JVM Advent
- Java Bad Partsにも挙げられるチェック例外をLambdaで扱うとき、ライブラリ使ってスッキリ書きましょう、という話。例外についての簡単な経緯とかもあるので、読んでみても良さそう。(個人的に気にせずtry-catch書いちゃってたな。)
7日目 Javaのパフォーマンスツールを覗いてみよう
A Sneak Peek at The Java Performance Toolbox - JVM Advent
- jcmdみたいな標準のパフォーマンス解析ツールの紹介
8日目 Javadocのコードスニペットとお友達
JavaDoc Code Snippets and Friends - JVM Advent
9日目 イベントに応じた処理の技術とメリット
The Art and Benefits of Computing Eventfully - JVM Advent
- イベント駆動アーキテクチャの入門みたいな感じ。ちゃんと読んでみてもいいかも。
10日目 KotlinとKotestによるプロパティベースドテスト
Property-based testing with Kotlin and Kotest - JVM Advent
- そのままの内容。個人的にプロパティベースドテストは探求したいテーマなので、ちゃんと読もうかな。
11日目 アクターと仮想スレッド。その組み合わせは天国か?
Actors and Virtual Threads, a match made in heaven? - JVM Advent
- アクターモデルを仮想スレッドで実装してみたって感じ。面白そうなので読んでみようかな。
12日目 開発者としてのキャリアをシニアレベルを超えていくための6つのアクション
6 Actions to take Your Developer Career Beyond Senior Level - JVM Advent
- 日本でも同じような議論があるなあ、という文化観察の意味で面白い。
13日目 GitHub のCIのYAMLファイルをどうやって、無くしたか
How I got rid of YAML in GitHub's CI - JVM Advent
14日目 Elasticsearch 8x 最新で、最高!
Elasticsearch 8x latest and greatest - JVM Advent
- Elasticsearchのアップデート情報。AWSと喧嘩してどうなっていくのかはちょっと興味深い。
15日目 クラウドネイティブ Javaの構成要素
Components of Cloud Native Java - JVM Advent
16日目 2つの輪の力。開発生産性への別の視点
The Power of Two Rings - Another View onto Developer Productivity - JVM Advent
- 開発者が行うinner loop(ローカルでコード書いて、テストしてってやつ)とプルリク後のレビュー/CI/CDでのouter loopの2つのフィードバックループがいいよって言ってるみたい。
17日目 Groovyとデータサイエンス
Groovy and Data Science - JVM Advent
- pythonじゃなくて、Groovyでデータサイエンスライブラリ使うって話のよう
18日目 Kotlinで非同期/関数型Webサーバー
Asynchronous Functional Web Server in Kotlin - JVM Advent
- Akkaやら仮想スレッド使ったWebAPIのパフォーマンス評価。仮想スレッドいいよ!って話みたい。
19日目 コミュニティのために、Javaをセキュアにしていく
Securing Java for the Community - JVM Advent
- Eclipse Adoptiumのセキュリティ担保のプロセス。ありがとうございます。お世話になってます。
20日目 実業務で品質ピラミッドにどう取り組んでいくか。
How to Tackle the Pyramid of Quality in the Real World - JVM Advent
- テストピラミッドのJavaでの実践編。いろんなブログとかでもあるけど、これもその一例として読めば良さそう。
21日目 Elasticsearchの内部
Elasticsearch Internals - JVM Advent
- 読んで字の如し。読んでみる。luceneってライブラリがベースなんだと。
22日目 JVM ハローワールド
- Hello Worldのクラスファイル/Java バイトコードを探求する系。
23日目 JavaギークにとってのWebAssembly
WebAssembly for the Java Geek - JVM Advent
- WebAssemblyの可能性について。単にブラウザ上の技術ではなく、プラットフォームになる可能性があるものだから、注視しようぜって言ってるみたい。個人的に「ブラウザの技術だから関係ないと思っちゃうかもだけど」って文脈で語られてて、あ、そういう感じなんだって思った。
24日目 PostgreSQLをメッセージキュートして使う
Using Postgres as a Message Queue - JVM Advent
- 読んで字の如し。Spring Integrationで機能があるのでその紹介がメイン。個人的に今メッセージキュー的なものの選定しているので、候補になるかなあ、と思うなどしている。。。
25日目 ACRUMEN:一体全体ソフトウェア品質とはなんなんだ?
ACRUMEN: What is "software quality" anyway?! - JVM Advent
- 品質特性の話。
まあ、レベル感としては日本と大差ないなあ、という感じ。
Temporal: 新しいワークフロー基盤を試してみようという話
Temporalとは
Uberで作られた信頼性の高いワークフロー/非同期実行基盤であるCadenceをforkして作られたもの。Cadenceを作った人たちがTemporal Technorogyというスタートアップを起業して作ったらしい。マネジメントサービスを提供してお金にしようとしているみたい。
なぜ試したいのか。
最初の動機は社内の昔ながらのジョブスケジューラ(日立のJP1/富士通のSystem Walker Operation Manager/IBM Tivoli/NTTデータのHinemos)から、もっとDev Opsとか開発者フレンドリーさであったり、クラウドとの親和性でったりしたものがないかと探していた。
ワークフローシステムとは
他の選択肢も色々検討してた。そもそもワークフローシステムと一口で言ってもかなり色んなユースケースだったり、ニュアンスの違いがある。自分が色々調べながら思ったのは以下のような分類。
システム運用/データ処理自動化
伝統的なジョブスケジューラは基本的には「システム運用」の自動化を目指したもので、インフラエンジニアとか運用エンジニア、今だとSREなんかが触るものとして設計されているように思われる。
Jenkins/Algo workflow/Apatche Airflow/Prefectなんかも結構その系統と思われる。
最近ではデータ分析が盛んになったので、プログラマーではないMLエンジニア、という新しいカテゴリも出てきたが、上記の比較的モダンなワークフローシステムはそういったニーズも意識して改善されているように思われる。
非エンジニア向けのローコードワークフロー
基本的にはアプリケーションの機能として提供されているもの。Saleforceであったり、oktaであったり、非エンジニアでも編集できるようになっている。
アプリケーションとしてのワークフロー
第3のカテゴリとしては、製品としてはActiviti/Camundaなどが該当する。よりプログラマーが扱うことを想定したワークフローシステム。
アプリケーションの中にワークフローが組み込まれるという形になる。多くの場合、そのアプリケーションはイベント駆動/非同期処理方式になり、その機能も備えている場合も多い。最近ではマイクロサービスを意識したSagaパターンの基盤として売り出そうとしているみたい。
ワークフローシステムの曖昧さ
ワークフローシステムは、結構面倒なのが、上記三つのカテゴリが意外とそれぞれが別のカテゴリの役割に担える傾向があること。伝統的なSIの開発では業務ロジックになる部分をジョブスケジューラのジョブネットで表現していた。結局ジョブスケジューラが無ければ、業務ロジックをテストできないってことになる。
プログラマー中心主義
自分のチームは基本は全員プログラマーで、どっちかというとプログラマーがインフラも見るって形になっている。当初はApatche AirflowやAlgo workflow(k8s使うので)を検討したのだけど、やはり、ワークフローを通常のコードと同じようなプロセスでテストやCIに乗せられるってこと、非同期処理なんかのニーズも増えていることもあり、3つ目のカテゴリであるActiviti/Camundaも試しに触って見てたりした。
そんな中、Java屋には有名なアメリカのソフトウェア開発コンサルティング会社Thoutworks のTechnorogy RaderにこのTemporalが紹介されていた。
Temporalのアーキテクチャと思想
システムアーキテクチャ
Temporalはワークフローを実行するworkerプロセスとそれを管理するサービス群(Temporal Cluster)の2種類に分けれれる。
Temporal Clusterはgoで書かれており、workerは様々な言語で開発可能なSDKが提供されている。gRPCでworkerとClusterは接続され、登録されたワークフローの実行をworkerが行う。Clusterはworkerがワークフロー実行することをリトライなどを駆使して保証してくれる。
これは、CEOの人がAWS/Azure/Uberなんかでやってて、得た知見をもとにしているみたい。
ワークフローの書き方
ワークフローはそれぞれのSDKで普通にプログラミング言語で書く。Javaだとインタフェースを駆使してかく。ワークフローの内部でActivityを呼び出し、その結果などを判定してフローをコードで書いていく。普通のコードなので、普通にテストが書ける。
TemporalではActivityはリトライを繰り返し、実行されることを保証させ、ワークフローは一度だけ確実に成功するってのが典型的な設計。リトライしないように設計することもできるが、その場合も実行するときにworkerが落ちてた時などはworkerが復旧して接続されるまで待ってくれる。これをTemporalはDurable Executionと言っている。
Activityは決定論的に記述することが推奨される。まあ、何度やっても結果が同じってことで冪等性ってことなのかな、と思っている。DBインサートとかの場合には、一意のキーを使ってそれを実現しろ、って言ってますな。
良いと思った点。
- 色んな言語でかける。ビジネスロジックはJavaで、基盤的なところはgoで、とか。
- プログラミングなので、なんかあってもどうにでもなる。
- ビジネスロジックと切り離せるため、移行が容易
- 信頼性の考え方がわかりやすい。
実は何より良かったのは、結構触ってみて、すぐ動かせたってこと。そして、複雑な要件を検討したところ、本当に色々考えられていて、かなり多くのユースケースに問題なく適用できそうってことを確認できた。
例えば、 - 長時間かかる大量ファイル処理 - ワークフローのアップデート/バージョンアップ - 監視/障害時調査と復旧 - 性能/データ量
チームのシニアエンジニアに見せても、パッと見て、「良さそう!」と印象を持ったとのこと。
加えて、slack見るとかなりちゃんとサポートしてくれているみたい。
実績
一応実績見ると、多分、CEOの人の人脈ありきだと思うけど、Netflix/ Datadog/ BOXみたいな誰もが知る優良企業でも使われているみたい。
Webアプリに適したものとそうでないもの
自分がここで書いたもの、WebAssemblyが広まっていくとちょっと変わっていくかもしれない。
----------
会社で自分が勧めて、neworkを使ってみてた。
結構評判が良くてみんな使ってくれてたんだけど、slackにhuddleができて、neworkが有料化するタイミングもあって、huddleに移行しちゃった。
neworkのコンセプトはとても良いし、個人的に、チームの外のひとが気軽に会話内容聞ける「聞き耳」機能は組織の風通しをよくする意味でとても良い、と思っていた。古い日本の会社でこれを作り出せるってのはとてもすごいと思う。継続して応援はしたい。
ただ、特にネットの状態が悪い時なんかは音質の劣化が激しい。出入りの際とか画面共有時にブツブツきれるみたいなものが解消されず、また、聞き耳機能みたいな物だったり、本当の雑談は一部の人しか活用できず、huddleと比較したら、有料Slackに追加でお金(手続きのコストも)を払ってまで導入するのはないな、という判断になってしまった。
個人的にWebアプリでやるべきものとそうでないものってあると思っている。RedmineみたいなのはWebと親和性高い。Webアプリとして使うもので、それが強みになるし、ホスティングサービスも有料でうまく行く。
一方でZoomがそうだけど、音声通話みたいなものってWebにしておくメリットってほぼないし、音声制御とかはネイティブアプリとかデスクトップアプリでガッチリ制御した方がいいと思う。huddleもweb版では利用できないっぽい。多分、技術的難しさがあるんだと思う。neworkは個人的にデザイン刷新なんか後回しにして、デスクトップアプリの開発に注力するべきだと思っている。
Webの思想と合わないってのはVS Codeもそう。JavaScriptとかは別かもだけど、Javaみたいな静的型付け言語を扱うのに、ブラウザベースのエディターってちょっと厳しい。あれが有料ならお金を払う人は少ないと思う。Intelij IDEAみたいにバリバリのデスクトップアプリにした方がいい。
同様に、業務システムなんかも基本、Webアプリとは相性が悪い場合が多いんじゃないかな、と。JetBrains Tool Boxみたいなアップデートを簡易にする方法を検討していくのがいい気がする。UXを求めるんならそこはコストのかけどころと感じる。「Quality is Free」なのだから。
APIテスト自動化ツールKarateをBDDツールとして使う
Karateとは
Karateは主にe2eテストを自動化するツール。cucumber的なfeatureファイルを書くとそれを実行できる。WebAPIのテストがその中心的ターゲット
graalvmのjsライブラリで実現しているっぽいので、featureファイルからJavaも呼べる。
個人的にBDDというのが結構いいと思っていて、ビジネスルールの仕様なんかをビジネスサイドと意識合わせする場合に使えると思っている。アンクルボブはFitnesseというツールを作っている。
Fitnesseは名著『実践アジャイルテスト』でも紹介されていたもの

実践アジャイルテスト テスターとアジャイルチームのための実践ガイド (IT Architects' Archiveソフトウェア開発の実践)
- 作者:Janet Gregory,Lisa Crispin
- 発売日: 2009/11/28
- メディア: 大型本
Fitnesseはアイデアはいいんだけど、wiki文書にテスト埋め込むとかまでしなくていいと思っていた。もっと簡便でメンテしやすい開発者フレンドリーなLiving Documentないかなあ、と。有名どころでは、Cucumberとかがあるんだけど、結局テストコードをドキュメントに合わせて2重に書くので、正直使いたくない。
Karateは簡潔なDSLでAPI呼び出しの実行からアサーションまでをfeatureファイルに記述できる。かなり文書性が高く、テストコード特有の煩雑なノイズがない。普通に開発者が使うテストツールとしても使えると思う。
一つ思ったのが、ビジネスルール単体の仕様についてkarateで同様にかければユーザーとのコミュニケーションに便利なのではないか、と。 加えてSpring のBeanもテストしたいと思ってやってみた。
featureファイルはこんな感じ。
Feature: ビジネスロジックのテスト
Background:
* def CalcTestsRunner = Java.type('feature.calc.CalcFeatureTestsRunner')
* table example
| 入力値1 | 入力値2 | 期待結果 |
| 10 | 20 | 30 |
| 50 | 100 | 150 |
| -10 | 10 | 0 |
Scenario: シンプルなシナリオ
* def x = 10
* def result = CalcTestsRunner.testAdd(x,20)
* assert result == 30
Scenario Outline: データ駆動シナリオ データ例 <入力値1> + <入力値2> の結果は<期待結果>になる
* def result = CalcTestsRunner.testAdd(<入力値1>,<入力値2>)
* assert result == <期待結果>
Examples:
| example |
テストコードはこんな感じ
package feature.calc; import com.example.demo.DemoApplication; import com.example.demo.calc.CalcService; import com.intuit.karate.junit5.Karate; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest; @SpringBootTest(classes = DemoApplication.class) public class CalcFeatureTestsRunner { static CalcService calcService; @Autowired public void setCalcService(CalcService calcService) { CalcFeatureTestsRunner.calcService = calcService; } @Karate.Test Karate testCalc() { return Karate.run("calc").relativeTo(getClass()); } public static int testAdd(int input1,int input2){ //仕様を実現するコードを書いていく。流動的で良い return calcService.add(input1,input2); } }
featureファイルにはプロダクションコードのクラスを直接書かない。リファクタリングするとき面倒になるから。 こんな感じで実行できる。

レポートはこんな感じ

githubにアップしました。
イメージ/観念と思考/行動